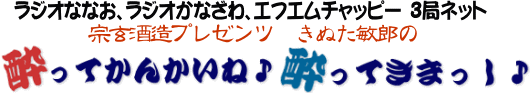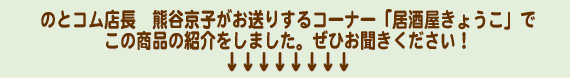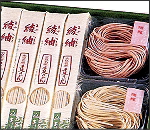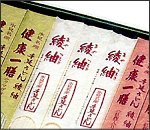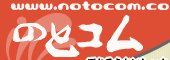
| HOME > �āE�݁E�� > ���ہE�����l�ߍ��킹 �@�c���c���Ƃ����A�����A�V�R�V�R�Ƃ������������A�����Ċ��Ƃ����ɍL���邤�܂݁B���̃o�����X��Nj����A�I�肷����̍��Y�������g���A�����đf�ނ̎��������\���Ɉ����o���Ǝ��̎艄�א��@�ɂ��ǂ���܂����B���ہi����ނ��j�́A�D��̎���ۂ��悤�ɁA���J�ɒ��J�ɐS�����߂Ă���܂����B �@�����ɂ��A�ۂ��`���K�^���ĂсA������^�Ԃ̂́u���v�Ȃ̂������ł��B������A����������X�ɍK���������Ē�������̂ł��肽���A����Ȋ肢�����߁A�u���v�̓�����͂��āA�X���艄�ׂ��ǂ�u�����i������イ�j�v�ƁA���g������A�N�}�U�T����̂��ǂ���ۂ��`�ǂ�A�����s�̖����E���������Z�E�l�̂����������������āu�����v�Ɩ��t���܂����B
���ہi����ނ��j ���_��̍��Y�������g�p���A������؎g�킸���˂��Ă��܂��B��H�������e�[�}�Ƃ���A���炾�ɂ₳�������N�H���ǂ�ł��B �����i������イ�j �K�^���^�ԂƂ����间�̓����Ɖߋ����疢���ɒʂ��鐅�̗����͂��Č^�ǂ��܂����B��H�����������p�b�P�[�W�ɓ����āA�������ɍœK�ł��B
�@�X���̎Y���͂��낢�날��܂����A���ɕ���ōŋ߃��L���L����o�����̎Y�i���������n�߂R�Ђ����������艄���ǂ��ł��B�זڂō��̋������̂��ǂ�́A���͖ܘ_�̂��ƁA���j�I�ɂ��Â��A�]�ǂ�A��낤�ǂ�ƕ�������{�R�傤�ǂ��ƕ��я̂���Ă���܂����A��ł����ǂ���\���{�Ƃ�����ԂƎ����������鐻�@�̌́A���Y�ʂ����Ȃ��A�u���̂��ǂ�v�Ɖ����Ă���܂����B �X���Ɍ��݂̂悤�Ȏ艄�א��@�ɂ�邤�ǂ`����ꂽ�͍̂]�˒����A���N�i�P�V�T�P�N�j�̂��Ƃ��Ɠ`�����Ă��܂��B �@�����A�֓��ɂ͉���˂̌�p�f�˂Ƃ��Ĕ����f�˂�����܂������A����ɐ��ނ��A�₪�Đ₦�Ă��܂��܂����B���ł͓��n�X���ƁA�X�����炳��ɓ`����ꂽ�Ƃ����v�g�s�̑��f�˂Ƃ��Ďc���Ă���킯�ł��B �@�Ȃ�A�֓��ɂ͂ǂ̂悤�ɂ��ē`����ꂽ�̂��A����ɂ��Q�̐����l�����Ă���悤�ł��B���̑�P�͌��݂̌`�̑f�ˁi�����͍��˂Ƃ����܂����j�͑T�m�ɂ������������`�����A�e�n�̑T���ɍL�߂�ꂽ�Ƃ�����̂ł��B �@�\�o��O���ɂ͑����@���{�R������������A���݂ł������̑m���͎l����i�C�s�m�������T���x�ޓ��ŁA�l�Ƌ�̕t�����j�ɂ͂��ǂ��H�ׂ�K��������܂��B�֓��̂��ǂ�͐悸�������ɓ`�����A��������L�����ԂɍL�܂����Ƃ�����ł��B �@��Q�͌����g�ɂ���ē`����ꂽ���̂��A��N�A�k�O�D�Ŋe�n�ɍL�܂����Ƃ�����B�H�c�̈�낤�ǂ�A���茧�E�ܓ��̌ܓ����ǂ�ȂǁA�X���ƕ��Ԏ艄�ׂ��ǂ�̌Â�����̎Y�n�́A���������{�C���Ɉʒu���Ă��܂��B�����́A���A�k�O�D�̊�`�n�ɂ��߂��A�֘A���l�����Ă���̂ł��B�k�O�D�̊�`�n�߂��ŁA���ǎ��̏����̎Y�n�ɎY�ƂƂ��Ă̂��ǂ�A�����߂��Ƃ��h�����̂ł͂Ȃ����Ƃ�����ł��B �@�֓��n���ɂ́A���ˋƂ����₦�����̂́A�\�o�����߂Ƃ������w���`�����Ă��܂��B����͐ΉP�ŏ�����҂����̉S���Ƃ����܂��B�x�R���ɂ́A��[�n��ɉz�������߂�����܂��B���ˋZ�@�Ƌ��ɖ��w�����A�`����ꂽ�̂ł��傤���B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �����̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂� �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �g�b�v�y�[�W�b���q�l�̐��b��ЊT�v�b���₢���킹�b���������@�b���ϕ��@�b�z�����@�b�ԕi�ƌ����ɂ����b���߂Ă̂��q�l���b�l���ی�ɂ����b�T�C�g�}�b�v�b�悭���鎿�� ���i�ꗗ�b���I�M�t�g�b�M�t�g�E�Z�b�g�b�ӂ��̍f�ЁE�����b�����b�Ђ����b�Е��b�Ă����b�����E�����b���X�E���E�ݖ��b�āE�݁E���b�a�m�َq�b���{���E�Ē��b��F�Ă� ���������\�o�ʔ̃T�C�g�I�l�b�g�ʔ́w�̂ƃR���x Copyright (C)�@2005�`�@�i�L�j�̂ƃR���@All Rights Reserved. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 �@�\�o�̖L���Ȏ��R�̌b�݂Ɠ`���̎葢��B�\�o�ɂ͏�L���Ȗ��킢���Ă���I �@�\�o�̖L���Ȏ��R�̌b�݂Ɠ`���̎葢��B�\�o�ɂ͏�L���Ȗ��킢���Ă���I�@�@�����ɁA�����Ă������ӂ̋C������Y�ꂸ�^�c���Ă���܂��B �@�@�u���O�@���������傤�� �@�@�{�C�X�u���O�@���͂͂̂ۂ� �@����낵���@(*- -)(*_ _)�y�R�� |
| �������ē� |
| �@���������@ |
| �@���ϕ��@ |
| �@�z�����@ |
| �@�ԕi�ƌ����ɂ��� |
| �@�悭���鎿�� |
| �@���₢���킹 |
| �@��ЊT�v |
| �@���菤����@�Ɋ�Â��\�L |
| �@�l���ی�ɂ��� |
| �@�T�C�g�}�b�v |
| �@�����N�W |
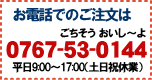
| �g�ѓd�b����� �������ł��܂��I 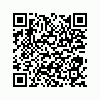 �̂ƃR��Yahoo!�X �i���o�C���p�j �@ |
| �@QR�R�[�h�Ή��̌g�ѓd�b�� �@QR�R�[�h���B��A�ǂݎ��܂��B �@���B�e���@�͊e�@��[���� �@�@�����������m�F�������B |
 |
�̂ƃR���̓v���C�o�V�[�ی�̂���SSL�Í����ʐM���̗p���Ă��܂��B |
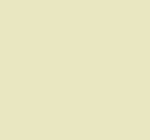
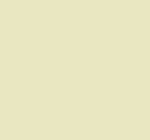
| �͋x�Ɠ��ƂȂ��Ă���܂��B |

| �y�̂ƃR���z�͌��I�@�ւł���ΐ쌧�Y�Ƒn�o�x���@�\����Â���o�[�`�������[���u���X����ISHIKAWA�v�ɔF����A�o�X���Ă��܂��B |
| ���{�ő�̃|�[�^���T�C�g�B �̂ƃR�����u�̂ƃR��Yahoo!�X�v�Ƃ��ďo�X���Ă��܂��B |

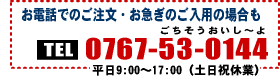

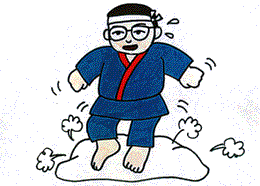


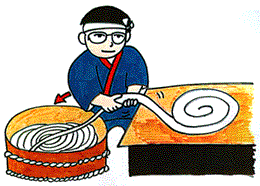
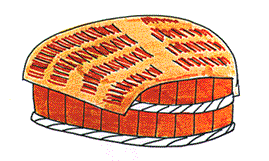
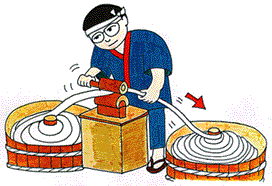
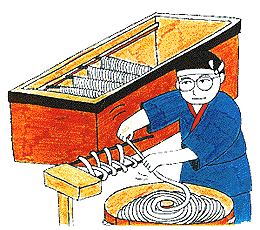
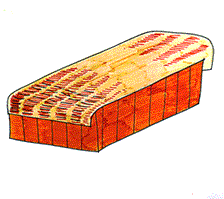
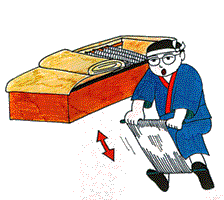
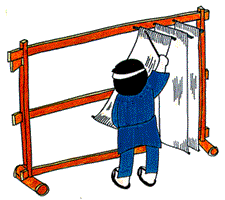
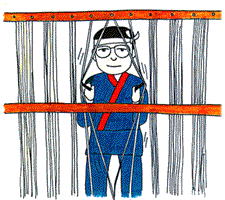


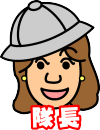 �y�X���艄�ׂ��ǂ�ɂ��āz
�y�X���艄�ׂ��ǂ�ɂ��āz